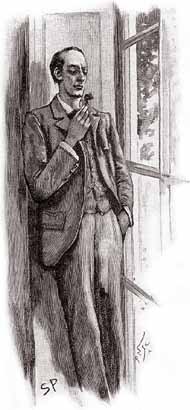エル・グレコの風景
エル・グレコ(1541年生~1614年没)の絵を初めて見たのは倉敷の大原美術館で、だと思う。なにせ昔の事で記憶も定かではないのだが、大原美術館には彼の「受胎告知」という絵がある。それ以来、エル・グレコは私のお気に入りの画家になっている。
スペインへ行きたい、と思ったきっかけの一つはエル・グレコの画集にあった、トレドの写真だった。彼の描いたトレド風景の絵と実際のトレドの写真を並べてあったのだが、中世に書かれた絵と現在の都市の風景とがほとんど変わらないのだ。
いくつもの国に分かれていたスペインの首都がマドリードに定められるまでの長い年月、首都とされていた。日本でいうと京都のような都市がその姿を何世紀もの間ほとんど変えていないとは。私はこの古都トレドを観たいと思ってしまったのだ。
トレドは湾曲するタホ川に三方を囲まれた岩山の上に築かれている。そして、残りの一方は高い崖になっている。つまり、防衛に最適な場所なのだ。以前、訪れたチェコのブルダバ川に囲まれた小都市チェスキークルムロフも同様だった。しかし、それより、「城塞都市」の感が強いのは、タホ川が深い谷を作っているせいだろう。
観光客は北側の崖下から街に入るが、見上げるような崖に今はエスカレーターが付けられている。これが無ければ街に入るだけでも一苦労だったと添乗員さんが言った。
「中世の人が現在に来ても、ちゃんと自分の家に帰れると言われています。」と添乗員さんがいかにこの街が変わらないかというエピソードを披露してくれる。この街は古代ローマ時代より、多くの他民族の支配下にあって、西欧の人々にもかなりエキゾチックに感じる景観らしく、多くの観光客が訪れる。遠くギリシャの出身であるエル・グレコ(ギリシャ人という意味)もこの都市を愛し、ここに住んだ。彼は中世の画家の常のように、教会や貴族の注文を受けて宗教画や肖像画を描く画家だったのだが、この街の風景を数多くの作品に忍ばせている。
さて、ようやく街なかに入る。イスラム圏の街のように街路は、細くくねくねと曲がり、さすがに「迷宮都市」の名にふさわしい。ここに「おのぼりさん」の我々(特に私)が放り込まれたら迷子は必須だ。そこで添乗員さんに必死でついて行く羽目になる。
観光名所である、トレド大聖堂の次に小さな教会に入った。なんだか人が多い。と、正面の祭壇を見て、あっと声を上げそうになった。壁一面の大きな絵はあのエル・グレコの「オルガス伯の埋葬」ではないか。グレコの代表作はここにあったのだ。不覚にも予見していなかった私めには大きな驚きだった。
サン・トメ教会に埋葬されているオルガス伯爵はこの旧いムデハル様式(イスラムとカソリックの混合した様式)の教会を再建し、ここに埋葬されている。その彼のお葬式の様子だ。上半分は雲の上でキリストや、天使たちが彼の魂を迎えるために集まっているという、グレコ特有の幻想的な光景で、下半分はお葬式の様子がリアルに描かれている。美々しい甲冑姿の故オルガス伯の顔は死者の灰色で痛々しいが美しい。これも美々しい衣装を着けた聖職者が遺体を運んでその背後に黒い正装の人々が参列している。彼らの顔が皆きちんと描かれているのは集団肖像画の意味があるのかもしれない。この絵を実際に観られただけでもトレドに来たかいがあった。
トレドを出た後、いよいよタホ川の対岸の展望台へバスで向かう。私の旅の目的の一つ、グレコの絵と同じ場所から写真を撮ることができる場所だ。ところが、多くの観光バスや車が集まっているために、展望台の近くに駐車できる場所がない。結局、そこからかなり離れた場所にバスが止められるはめになった。
そこからもトレドの街の全景は見ることはできるのだが、私が思う角度ではなかった。そこで、さっきの展望台のところまで短い自由時間の間に走って戻ることにした。
エル・グレコの絵にはタホ川を渡る古い橋が描かれている。その橋を遠く望むところがいい。ところが展望台の所まで戻っても橋は見えない。もっと先へタホ川沿いに行かねばならないのだろうが、その時間はなかった。仕方ない。そこから街の風景をカメラに収めて、今度はバスが待つ所まで走ることになった。なんともせわしない。でも、お仕着せのツァーなら、仕方ないか。
陽光の中に輝く古都トレドはさすがに美しく、まさに絶景。何度も支配者を変えながら、その姿を保ち続けたトレド。この風景を観に、私はこのツァーに参加したのだ。